もくじ
1. 【誰に向けて書くか】を明確にする
キャッチコピーは「ターゲット次第」で言葉が変わります。
たとえば、同じ商品でも…
若い女性向け → 「キレイになりたいあなたへ」
会社員向け → 「疲れた夜に、ひと息つく時間を」
など、相手によって言葉の刺さり方がまったくコピー変わります。
ペルソナ(具体的な人物像)を1人決めることで、刺さるコピーが作りやすくなります。

2. ベネフィットを伝える
商品の特徴(スペック)ではなく、「使ったあと、どうなるか?」を伝えることが重要です。
NG:「高濃度ビタミンC配合」
OK:「透明感のある、うるツヤ肌へ」
人は「自分にとって得かどうか」で動きます。
機能ではなく、消費者の未来の姿を見せてあげましょう。
3. 意外性やギャップを盛り込む
読み手の「えっ!?」という感情を引き出せると、心をつかめます。
▶ 例:
「日本一まずいラーメン屋」
↓
逆に気になる
「3日で辞めた会社に、今感謝している」
↓
続きを知りたくなる
人は違和感に反応します。
常識を少しズラす発想がキーポイントです。
4. 音のリズムを意識する
キャッチコピーは目だけでなく、耳でも読まれています。
声に出したときにリズムがよいか、語呂がいいかを意識しましょう。
▶ 例:
「うまい、早い、安い。」
「お金より、大事なものがある。」
五七調や三段構成(例:◯◯、◯◯、◯◯)など、音の響きが良いと記憶に残りやすくなります。
5. 多数のキャッチコピーを考える
プロでも、1本目で決まることはほとんどありません。
最低でも30本くらいは書いてみましょう。
その中から「これだ!」という1本を選びます。

6. 言葉の「温度感」を合わせる
商品の世界観とコピーのトーン(言葉の温度)がズレていると、読まれません。
高級ブランド → 「あなたを格上げする、一着。」
大衆向け → 「毎日着たくなる、ふつうがいちばん。」
カジュアルにするか、フォーマルにするか。
柔らかい言葉か、硬い言葉か。
言葉の選び方ひとつで、ブランドイメージが左右されます。
7. 読み手の「言いたかった言葉」を代弁する
自分でも気づいていなかった「本音」をズバッと言い当てられると、共感が生まれます。
気づいていない本音とは、「インサイト」とも言います。
▶ 例:
「ちゃんとしなきゃ、に疲れたあなたへ」
「もう、“普通”に戻らなくていい。」
読者の心の中のセリフを想像し、それをそのままコピーにします。
共感こそが、心を動かす第一歩です。
8. 「行動」を促す言葉を入れる
人を動かすキャッチコピーには、読んだ後に「何かしたくなる」力があります。
▶ 例:
「今すぐ、鏡を見てください。」
「あなたも今日から、始めませんか?」
単なる説明ではなく、行動の呼びかけを入れるという手法もあります。
特にWeb広告はDMなどで有効です。
9. 否定・反論を先に入れる(あえて逆をつく)
「でも」「しかし」「とはいえ」で始まるコピーは、人の注意を引きます。
▶ 例:
「ダイエットに失敗したあなたに、聞いてほしい。」
「お金がない。でも、夢はある。」
あえて読者の不安や反論を先回りして認めることで、信頼感と関心が生まれます。
10. コピーを「詩」として読んでみる
プロのコピーは「詩」としても読めるほど美しい構造になっていることもあります。
▶ 例:
忘れられない夏がある。
それは、冷たくて、熱かった。
構成、リズム、余白を意識すると、コピーの表現力がぐっと上がります。
11. 1単語で世界を変える:「言い切り・断定」で強くする
ふわっとした表現ではなく、「言い切り」にするだけでコピーの説得力が爆上がりします。
▶ 例:
△「きっと、変われるかもしれない」
◎「変われる。絶対に。」
断言することで読み手の背中を押す力が生まれます。
12. 余白で読ませる:「あえて書かない」勇気
プロは「説明しすぎない」ことを大切にします。
あえて曖昧にすることで、読み手に想像させ、感情移入を促します。
▶ 例:
あの夏、
僕らはまだ、
知らなかった。
このように、余白や行間の使い方が上級者の証です。
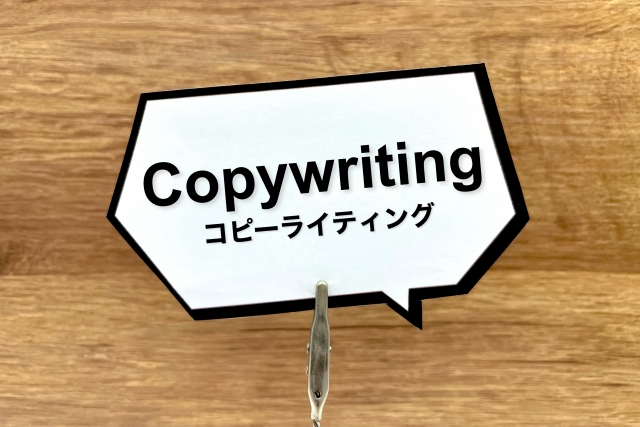
13. ひとことの「引っかかり」をつくる
すらすら読めるコピーより、「ちょっとひっかかる」コピーのほうが記憶に残ります。
▶ 例:
「恋より、うまいかも。」
「人生、味つけが9割。」
この“引っかかり”は、言葉遊び・比喩・倒置法・矛盾表現などでつくれます。
14. 自分に話しかけられているように感じさせる
コピーに「あなた」「君」「〇〇さん」などの呼びかけ言葉を入れると、グッと距離が近くなります。
▶ 例:
「そこのあなた。その悩み、そろそろ終わりにしませんか?」
「君の未来に、火を灯すノート。」
まるで自分のことを見ているかのように感じさせる。これが刺さる秘訣です。
15. 「対比」でインパクトを出す
人は比較されることで強く印象を受けます。あえて真逆の言葉を並べてギャップをつくる技法です。
▶ 例:
「過去は捨てた。未来だけ着る服。」
「強くなりたい。弱さを受け入れたその日から。」
このコントラスト効果は、深く刺さる表現をつくる上で非常に有効です。
16. 「事実 × 感情」で仕上げる
ただの事実に、感情のスパイスを加えると一気に人の心に刺さります。
▶ 例:
「糖質80%オフ。だから嬉しい。」
「年間1万個売れてます。理由は、食べればわかる。」
ロジック+エモーションの掛け算が、納得と共感の両方を生みます。
17. 「他の言葉」を参考にする
実はプロは、生活者のリアルな言葉をコピーにすることがあります。
▶ やり方:
SNS、口コミ、レビュー、掲示板などを見る
その中から「感情がこもった言葉」「ちょっと変わった表現」を抽出
それを磨いてキャッチコピー化する
▶ 例:
口コミ:「このクリーム、夜塗ると朝モチモチで感動した!」
→ コピー:「朝、モチモチの奇跡を起こすクリーム。」
“作る”より“拾う”方が、刺さる言葉が見つかることも多いです。

18. 読み手の「自尊心」をくすぐる
プロのコピーは、読者の自己肯定感やプライドを満たす設計がされています。
▶ 例:
「あなたには、選ぶ自由がある。」
「流されないあなたへ。」
「ちゃんと頑張ってる人だけに。」
誰でも「自分は特別」と思いたい生き物。その承認欲求を言語化することがコツです。
19. 「後ろに本音を入れる」テクニック
コピーの最後に「ズバッと本音」を差し込むことで一気にインパクトを与えます。
▶ 例:
「私は、私を諦めない。──もう限界だけどね。」
「ダイエットに成功しました。3日だけだけど。」
この“オチ”があることで、共感・驚き・笑い・リアリティが一気に高まります。
20. 「知らなかったこと」で始める
人は、“自分が知らなかった事実”を見たとき、自然と続きを読みたくなります(カリギュラ効果)。
▶ 例:
「知らないうちに、3kg痩せてた話。」
「99%の人が気づいていない、睡眠の事実。」
“気になる導入”があると、自然に続きを読みたくなります。
21. わざと「違和感ワード」を入れる
あえてちょっと引っかかる言葉や文法ミスっぽい言葉を入れると、脳が「なんだ?」と反応します。
▶ 例:
「大丈夫じゃないのに、大丈夫って言うあなたへ。」
「やばい、野菜がうますぎる。」
正しさより“面白さ”や“リアルさ”を狙いに行くテクニックです。
22. 読後に「勝手に続きを考えてしまう」終わり方
あえて途中で止めることで、脳が勝手に続きを妄想します。
▶ 例:
「君が笑った。僕は、」
「本当は、全部言いたかった。」
この「読後の余韻」は、記憶に残りやすく、感情に深く刺さる技法です。
23. 「お客さんが絶対に使わない言葉」は使わない
プロは、専門用語やマーケティング的な言い回しを避けます。
なぜなら、読み手の脳内に存在しない言葉はスルーされるからです。
×「ROIが高い商品設計」
〇「ムダなお金を使わずに、ちゃんと売れる。」
コピーは“読まれる”前に、“理解される”必要があります。


